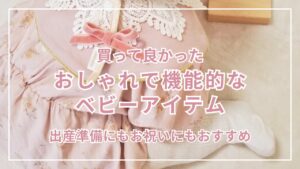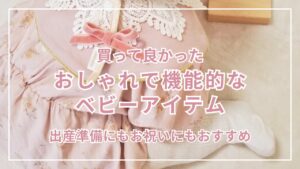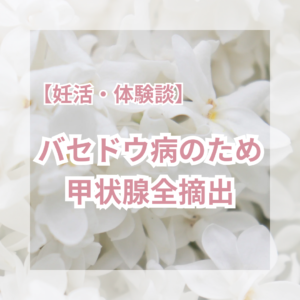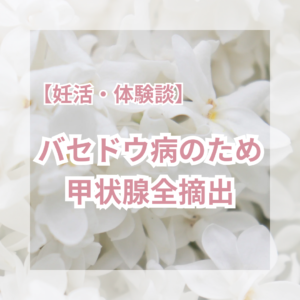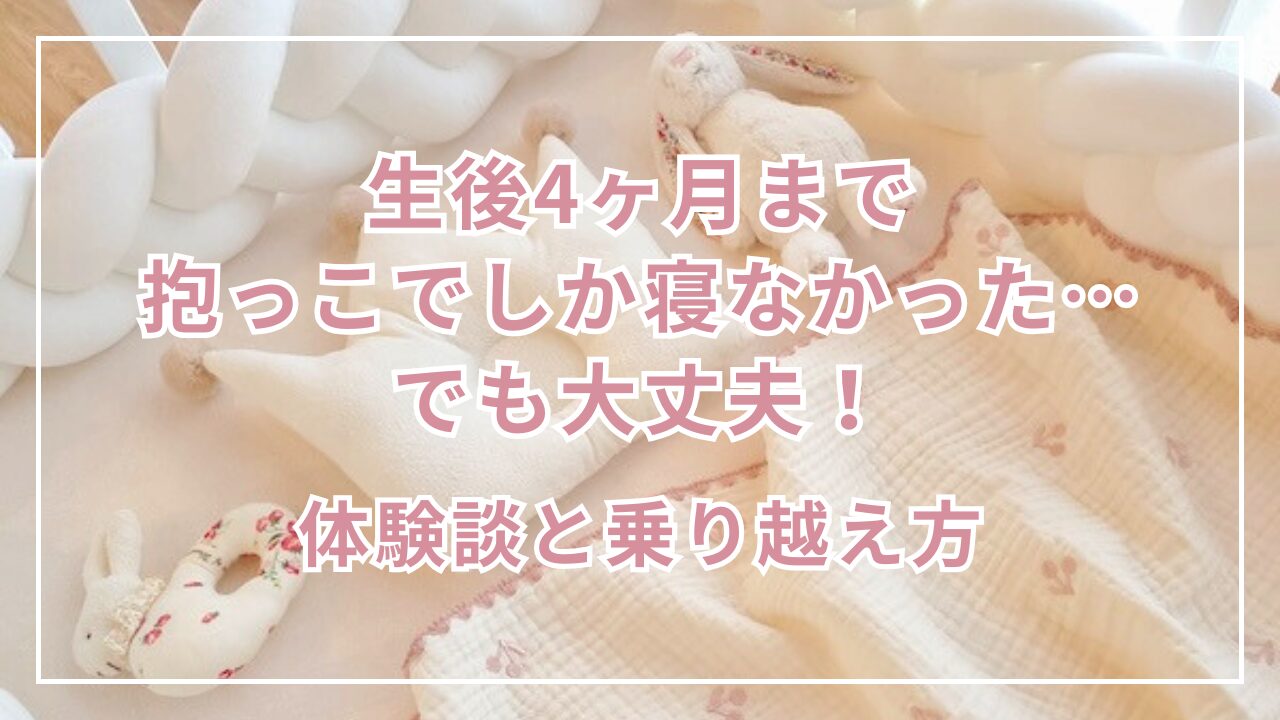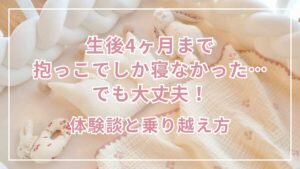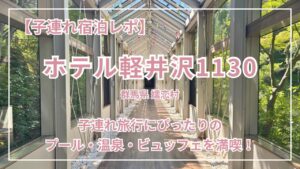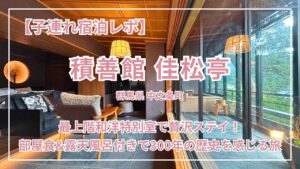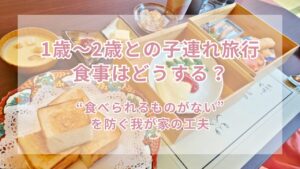生後0〜4ヶ月の赤ちゃんが「抱っこでしか寝てくれない…」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
布団にそっと降ろした瞬間に泣かれてしまい、結局ずっと抱っこ。体も心も休まらず、出口が見えないように感じてしまいますよね。
私も同じ経験をしました。昼も夜も抱っこで、家事は抱っこ紐をつけたまま。家はごちゃごちゃ、頼れるのは夫だけ。しかも母乳が出ずに完ミとなり、「母乳で育てなければ」と思い込んでいた私は、自分を責めてしまうことも。
産後2ヶ月頃まではホルモンバランスも乱れて気持ちが落ち込み、夫が「大丈夫だよ」と励ましてくれても素直に聞けませんでした。
この記事では、生後4ヶ月まで抱っこでしか眠れなかった娘の様子、当時の工夫、そして変化していった体験をお伝えします。
生後4ヶ月まで抱っこじゃないと寝なかった理由とは?
赤ちゃんが抱っこでしか眠れないのは、安心感を求めているからかもしれません。抱っこをされると鼓動や体温を感じ、心地よさに包まれて眠りにつきます。
私の娘もまさにそうでした。昼間は一度もベビーベッドでは寝ず、置いた瞬間に泣き出す毎日。
さらに、生後4ヶ月までは睡眠リズムも安定していません。布団におろすとすぐ目を覚ましてしまうことも多く、それが「抱っこじゃないと眠れない」状況につながっていました。
このように、娘が抱っこでしか眠れなかったのは自然なことでしたが、当時は本当に大変でした。
実際の毎日がどうだったのかを紹介します。
生後4ヶ月まで抱っこじゃないと寝なかった我が子の様子
生後2ヶ月までは、昼間は常に抱っこで、私が体を離すと泣き出してしまいました。洗濯も料理も抱っこ紐をつけたまま行い、家の中は片付けられずごちゃごちゃ。夫が仕事から帰宅後に掃除や買い物をしてくれて、本当に助かりました。
夜も抱っこは続きました。ミルクを欲しがって泣き出し、授乳後もほとんどが抱っこのまま。私はソファに座ったまま抱っこしてうたた寝し、夫と交代で夜を乗り越えました。夫も寝不足だったと思います。
徐々に機嫌の良い起きている時間も増え、そのときは抱っこせずに過ごすことができました。しかし眠くなると泣き出して抱っこ。寝てからそっと布団におろしたら泣いてしまうので、寝ている間は抱っこし続けます。

勇気を出して参加したベビーマッサージでは、泣いてばかりで何もできず、結局ずっと抱っこ。
実家も遠く、友達もいない土地での育児。夫が仕事に行くたびに「私一人で大丈夫かなぁ」と不安になることもありました。
背中スイッチで泣く赤ちゃんとの日々
抱っこで寝かしつけても、布団にそっと置いた瞬間に泣き出す…。まるで背中にスイッチがあるかのようで、本当に困りました。
おくるみ、おしゃぶり、電動のスイングハイローラック、布団をあらかじめ温めてみたり、置いたあとに背中を優しくトントンしてみたり、ミルクの間隔を変えてみたり、できることは全て試しましたが、結果は同じ。
背中スイッチが発動して、あっという間に泣き声に変わってしまいました。
そのため、お昼ご飯を食べる時間も取れず、気付けば抱っこしたまま夕方を迎えてしまう日もありました。
赤ちゃんにとっては安心できる方法なのだと分かっていても、毎日続くと心身ともに疲労が積み重なっていきました。
生後4ヶ月まで抱っこじゃないと寝なかった時期の工夫
散歩
一番の救いは散歩でした。
生後1ヶ月以降は、雨でなければ毎日散歩に出かけました。ベビーカーや抱っこ紐で外に出ると、娘は不思議と泣かず、キョロキョロと景色を見回したり、空や木々をじっと眺めたりしていました。
外の空気や太陽の光は、私自身の気持ちも軽くしてくれました。どんなに疲れていても、散歩だけは欠かしませんでした。娘も散歩中にそのまま眠ることも多く、その間は公園のベンチに腰掛けてコーヒーを飲んだりしました。
夫が休みの日は、動物園や大きな公園に行きました。
ふれあい時間
生後2ヶ月を過ぎた頃から、少しずつ機嫌よく起きていられる時間が増えてきました。新生児の頃は抱っこで泣き続けていた娘でしたが、この時期になると笑顔が見られるようになり、心が救われる瞬間が増えていきました。
日中はマットにごろんと寝かせて、絵本を読んだり、おもちゃやぬいぐるみで遊んだり、一緒にふれあい遊びをすることもできるようになりました。
まだまだ寝るときは抱っこが欠かせませんでしたが、それでも可愛い仕草や笑顔のおかげで「大変だけど楽しい」と思える時間が確かにあったのです。
育児の大変さに押しつぶされそうなときも、この短いふれあいの時間があったからこそ乗り越えられたと今では感じています。
添い寝
生後3ヶ月頃からは添い寝に近い形を取り入れました。
ベビーベッドでは眠れなかった娘も、私の隣だと比較的落ち着いて眠れるようになりました。
夫の支え
夫に短時間でも抱っこを代わってもらい、その間に体を休めました。ほんの少しでも休む時間があると、気持ちが前向きになれました。
夫は、買い物や掃除などの家事も積極的にやってくれました。私の好きなスイーツを毎回買ってきて、夫が娘を抱っこしている間に食べ、とても元気が出ました。



このような小さな工夫を重ねながら、抱っこ漬けの日々を乗り越えていきました。そして、生後4ヶ月を過ぎると大きな変化が訪れました。
生後4ヶ月を過ぎてからの変化
生後4ヶ月を過ぎると、娘は自然と夜にまとまって眠れるようになりました。夜中に何度も起こされなくなり、授乳後も添い寝で眠ってくれることが増えていきました。夜にしっかり眠れるようになったときの喜びは、言葉では表せないほど大きかったです。
まとまった睡眠が取れるようになると、私自身の心が軽くなり、精神的にも元気を取り戻せました。それまでは母乳で育てられなかった自分を責めていましたが、「完ミでも大丈夫」とようやく思えるようになりました。
気持ちに余裕が生まれると、離乳食の準備をしたり、ハーフバースデーを計画したり、地域の子育てイベントに参加するようになりました。孤独感に押しつぶされそうだった日々が少しずつ変わり、育児を楽しむ時間へと変化していったのです。
さらに嬉しいことに、生後8〜10ヶ月頃には周りの友達が夜泣きで悩んでいる中、娘は夜泣き知らずで安定して眠ってくれました。
生後8ヶ月には、初めての子連れ旅行で伊香保温泉へ行きました。
その後も睡眠の悩みはなく、現在4歳になった今でも早寝早起きを続け、寝起きもとても機嫌が良いです。抱っこでしか眠れなかった時期があったことが信じられないほど、睡眠面では育てやすさを感じています。


まとめ
生後4ヶ月まで抱っこじゃないと寝なかった娘との体験を通じて、抱っこを求めるのは自然なことだとお伝えしました。昼も夜も抱っこ続きで、母乳へのこだわりから心も弱り、孤独を感じる日々でしたが、散歩や添い寝の工夫、夫の支えで乗り越えることができました。
そして、生後4ヶ月を過ぎると眠りは安定し、精神的にも前向きになれました。
「赤ちゃんの睡眠習慣は千差万別」です。中には寝かしつけをしなくても自分で眠りに入れる子もいれば、抱っこでしか眠れない子もいます。どちらも決して特別なことではありません。
育児は思い通りにいかないことばかりですが、必ず変化の時は訪れます。無理をせず、周囲の協力を得ながら過ごしていきましょう。
今では夜泣きもなく、早寝早起きで元気に過ごす4歳の娘。今も疲れたときや甘えたいときは、抱っこを求めてきます。もちろん喜んで抱っこしてあげます。
抱っこでしか寝なかった日々も、今振り返れば宝物のような時間だったと感じています。抱っこの時間があったからこそ娘は安心していられたのだと思います。